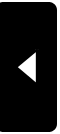2012年06月25日
近江学園を訪れて
 先日、近江学園に立寄る機会を得ました。
先日、近江学園に立寄る機会を得ました。父が社会福祉の仕事をしていたこともあり、近江学園は戦後日本の先駆的な知的障害児の施設と聞いていました。
案内して頂いた方に訊くと「ここは糸賀一雄先生らが昭和21年に滋賀県立の施設として創設されました。」とのことでした。
糸賀先生は「この子らに光を」ではなく「この子らを光に」と施設の運営方針を示されたそうです。
全国の同じような施設と同様に、生徒は近江学園に入所して生活しているため、職員は生徒が学校にいくまで6時から9時、生徒が学校から帰る15時から21時までの変則勤務になっており、本当にご苦労なことです。
最近の宿舎は大きくなって数十人が生活しています。
確かに食事や介護の効率は良いのですが「生活のゆとりはどうかなぁ」と思っておりました。
ところが近江学園は十人前後が生活できる宿舎規模になっており、効率よりも生活のゆとりを大事にしておられるそうです。
かつて父が岡山県に知的障害児の施設(ももぞの学園)を創った頃、安普請ではありましたが、一つの宿舎に数人前後が生活していました。
それが、今では数十人が生活する宿舎をもつ施設に変貌しています。
こんど岡山県に行ったら、ももぞの学園の理事長に近江学園の宿舎規模について伝えようと思います。
いってん
Posted by
西日本技術の環境調査員
at
07:28
│Comments(
0
) │
暮らし