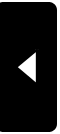2008年09月17日
水道産業の海外進出
日本国内の水道産業は、高い普及率と公共投資の減少によって大きな曲がり角に来ています。また、今後、日本の人口が減少することによって、さらに市場規模は縮小へと向かいます。そこで国内の水道産業が一丸となって連携し、国際的な市場へと展開する動きが出始めています。今日はこの問題のうち、国際競争入札について考えてみます。
国際競争入札は、無償援助や技術協力を除き、応募者の資格に国籍などの条件をつけることは禁止されています。したがって、日本の資金援助によるプロジェクトであっても、日本の企業が優遇されることはありません。このため、日本の資金で海外の会社が水道施設を建設し、運転管理まで行う事例が多数発生し、日本の水道産業には何もメリットのある仕組みにはなっていません。
なぜ、このような状況になるのでしょうか?
答えは簡単で「応募資格がない」。では、国際競争入札の応募資格を見てみましょう。この事例は、ある国の発展途上国の水道事業の応募資格です。
業務実績
・ 途上国を含む2カ国以上で水道事業運営の実績
・ 拡張事業の事業管理(資金調達(5年間で2,000万US$(約22億円))、工事実施など)の経験を有すること
経営基盤
・ 必要な資格(総括、運転管理、工事、財務の責任者は15年以上の経験)
・ 経営状況が良好であること(1億US$(110億円)以上の売り上げを上げている、利益を世界全体から継続的に上げている)
この条件を満たして応募できるのは大手商社だけです。水道産業に属する企業単独では国際競争入札には参加できません。日本の水道ビジネスはEPC(技術、調達、建設)がバラバラに存在し総合的な水会社がなく、サービス提供(運転管理、料金徴収、需要者サービス等)の民間委託が可能になって数年しかたっていません。したがって、多くの会社は実績不足に陥っています。
<打開策は>
基本的にODAの無償援助のタイト(ひも付き)で実績を積み上げるしかありません。
また、水道協会等の独自基準を捨て、世界の基準で統一していく必要があります。これは野球と同じでボールの大きさ、テレビ画面のストライク・ボールの並べ方と同じです。
あとひとつは、価格競争に負けない対策が必要です。途上国のニーズはハイスペック製品の必要はありません。価格的にはおよそ3分の1程度の製品が求められます。これは日本の携帯電話と同じです。
水道産業の製造分野も曲がり角ですね。
Posted by
西日本技術の環境調査員
at
07:28
│Comments(
0
) │
水道