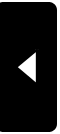2009年03月02日
日本とドイツの水ビジネス
水資源は、国益や国民の生命・安全に直結する根本的な天然資源です。しかし、洪水が多発する一方で水不足はアフリカ、地中海沿岸地域、オーストラリア、中国、北米そして南米でも拡大し続けています。
しかし、水は根本的な資源であるにもかかわらず、技術、維持管理、事業経営だけではなく、市場開発力、建設資金調達力、M&A能力などは国の政策によって大きく異なります。全体的にはフランス(ヴェオリア、スエズ)、イギリス(テムズ)、アメリカ(GE)が大きくリードし、ドイツが続き、大きく遅れて日本の順番になります。
なお、アメリカのGEは北京オリンピックの「鳥の巣」浄水を担当しています。
このうち、高い水関連技術を有し水市場分野で一定の規模を占めてはいるものの、総合力で出遅れているのが日本とドイツ。技術先進国の自負はあっても、自国内の経営資源を効果的にまとめきれず、大型プロジェクトや革新的プロジェクトへの参加ができない現状が続いています。そこで新しい流れが登場。
<ドイツ>
ドイツ電力大手2社が国際水市場に参加するも経営力不足で敗退。現在は最大重電メーカーのシーメンスが参入。なお、シーメンスは上海の富裕層を対象に、中国のドイツ系大学と共同で病院経営にも乗り出しています。
しかし、100年の歴史をもって先行するフランス、そしてイギリス、アメリカの姿ははるか遠く。そこで昨年、ドイツは統一ブランド「German Water Partnership」を設立。
これは企業間の連携に留まらず、官民相互の連携を図り国際進出を狙いとしています。
<日本>
日本は海水淡水化に使用される水処理膜、排水処理技術は世界的に評価されている技術。部品メーカーとしての営業活動は行っていたものの、アジア、産油国に対する水市場開発を実態的に行っておらず、政府・大使館の支援もなく国際水市場に出遅れることになった。
これに対して、今年、プラントメーカーやゼネコンの30社近くが「海外水循環システム協議会」を設立。政府も日本政策金融公庫・国際協力銀行の融資、貿易保険制度の活用、政府開発援助(ODA)の供与を検討。
<これからですが>
日本国内でも水道事業の民営化が遅れ、非効率の水道事業を行政改革することもできない。現状の水道事業における民間企業への第三者業務委託は限定的であって、世界水準の水ビジネスとは全く異質。日本の技術力が評価されているといっても限定的。
日本とドイツの共通点は官民が一体となって海外進出。ドイツはもうひとつ。大学や研究機関も参加しています。残念ながら、今のところ日本では参加しておりません。
市場として期待が持てる中国進出は、韓国の企業もすでに中国企業と合弁会社を設立しています。出遅れた分だけ、実績をつけるために日本のお金で中国の上下水道を建設・管理・経営していかなければなりません。
Posted by
西日本技術の環境調査員
at
07:28
│Comments(
0
) │
水道